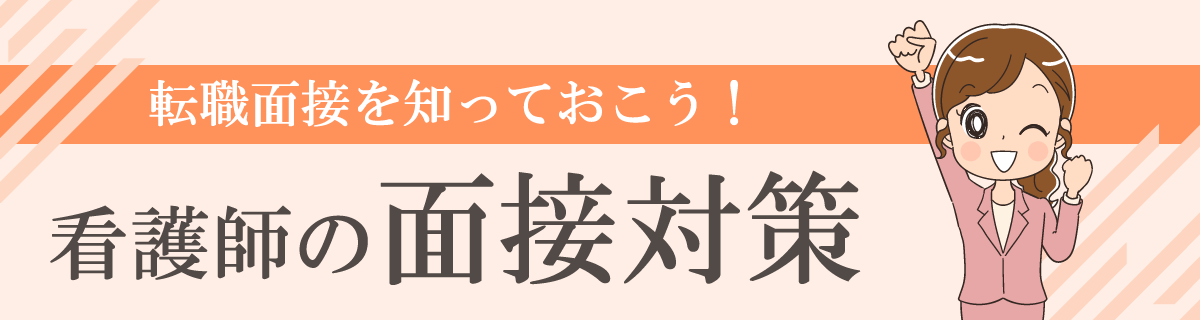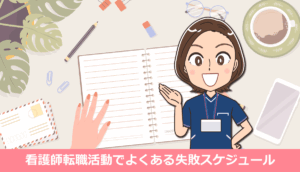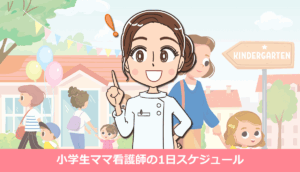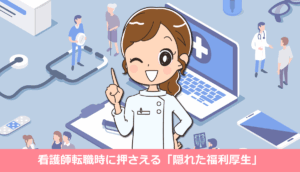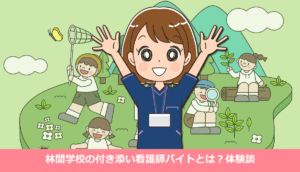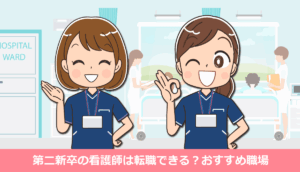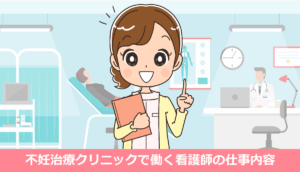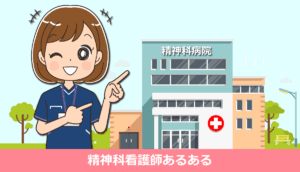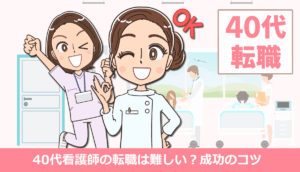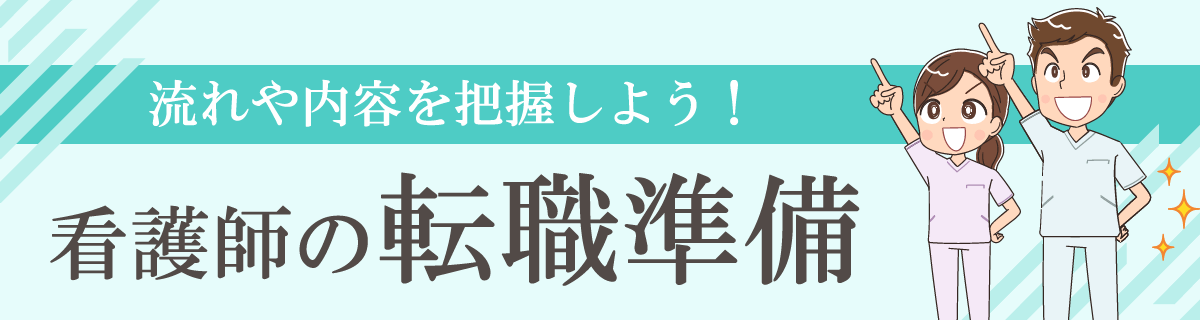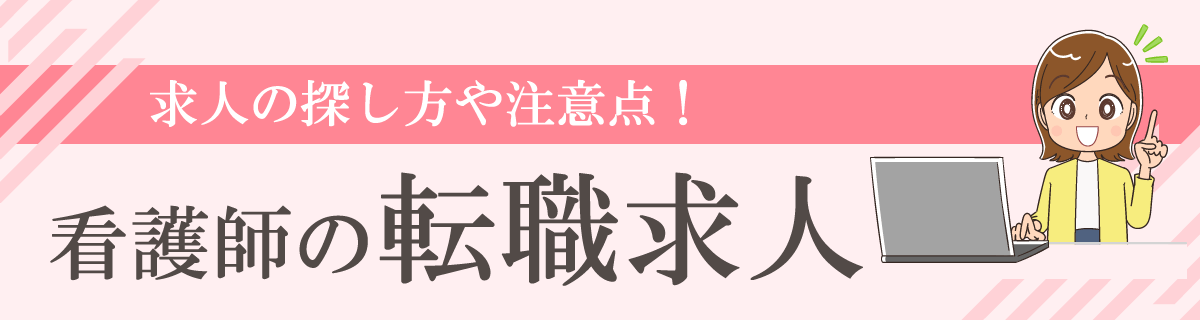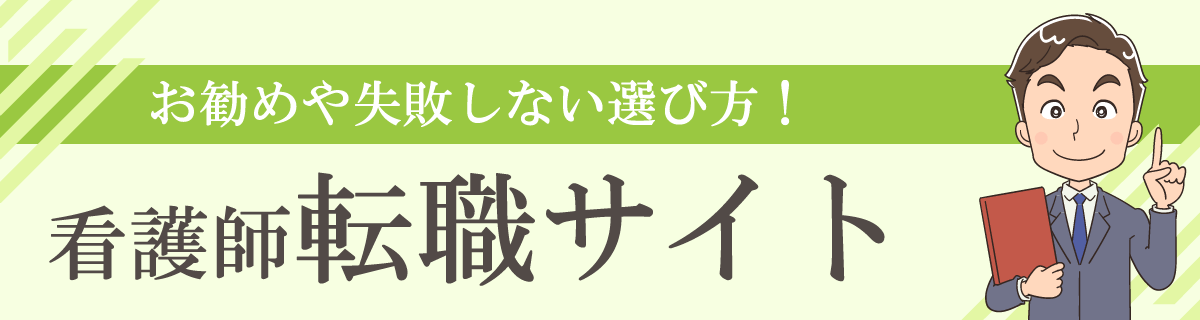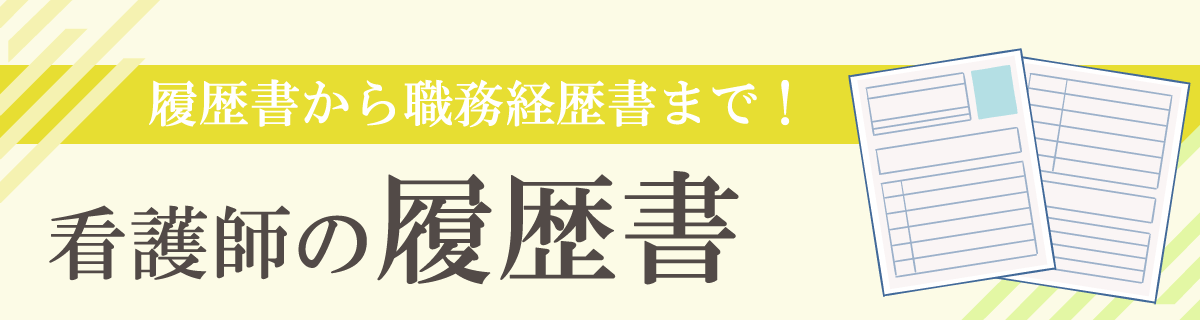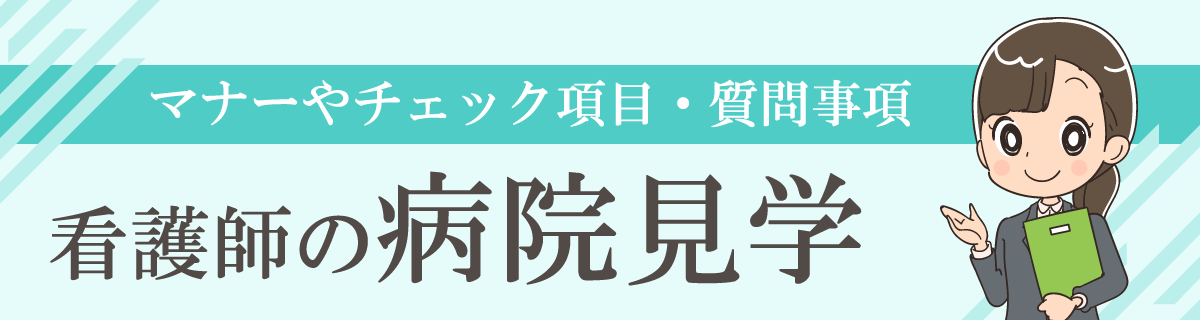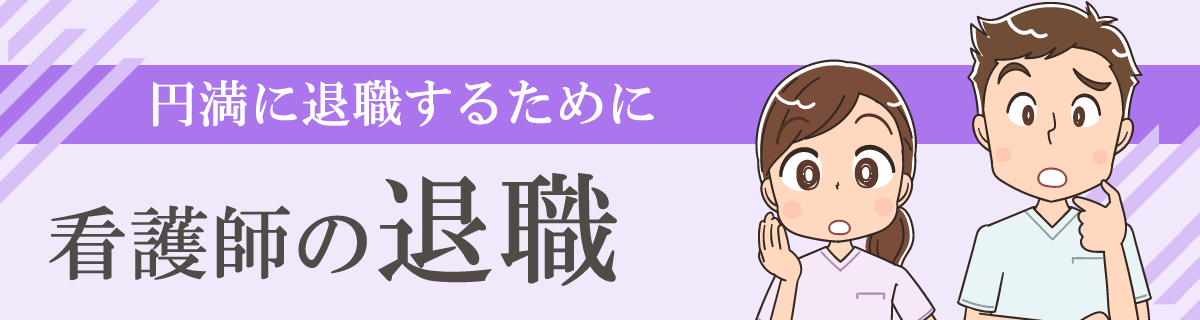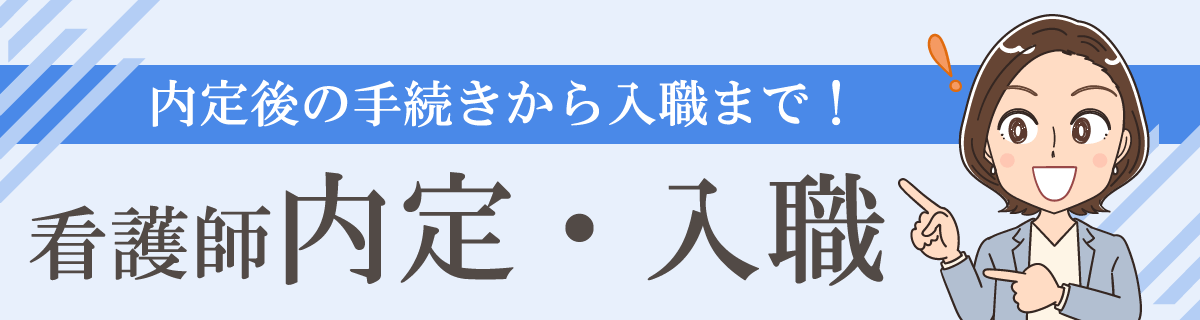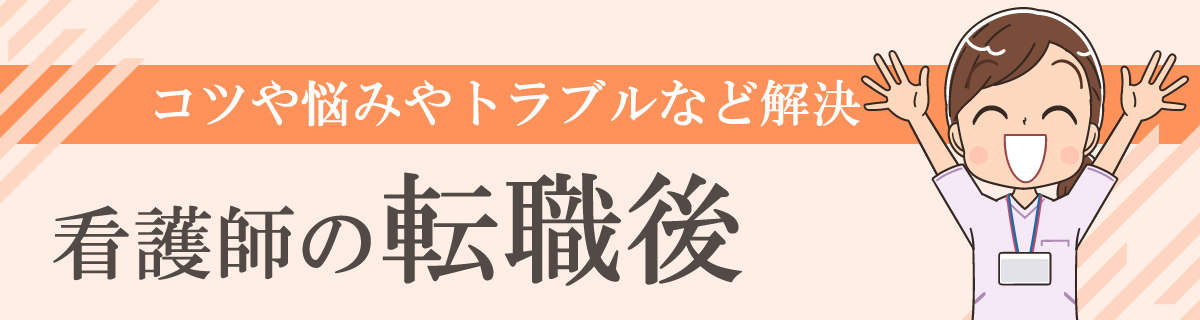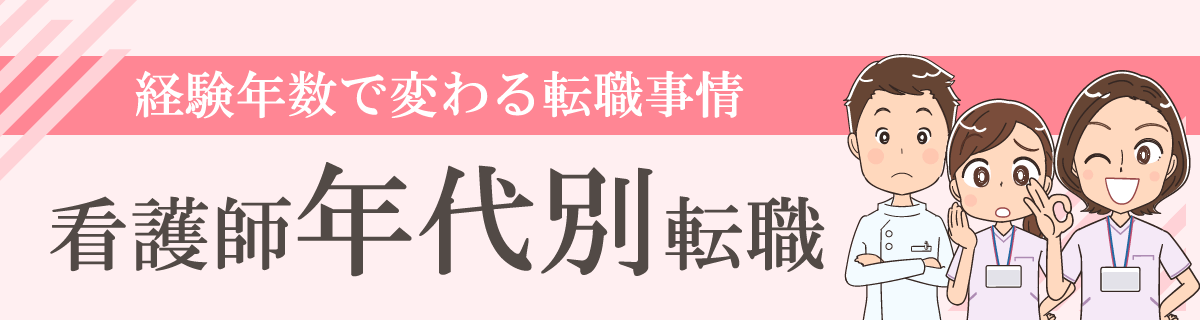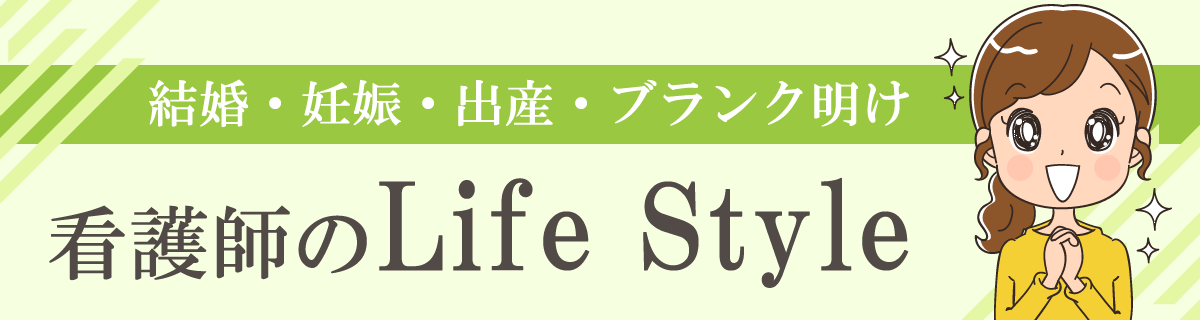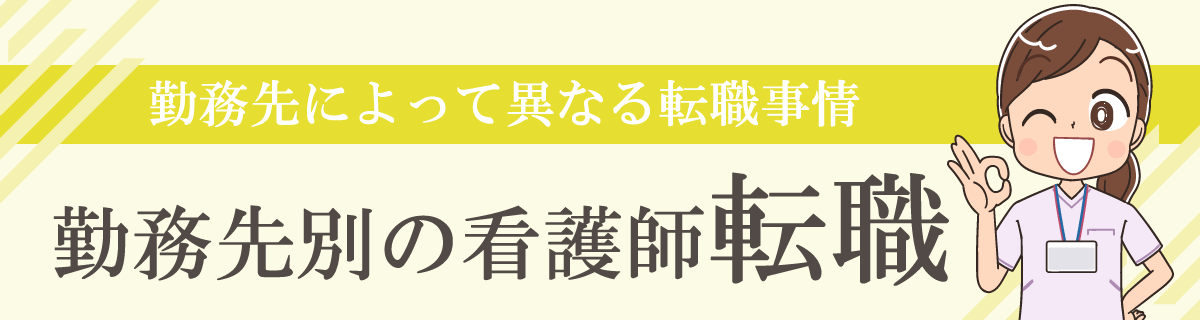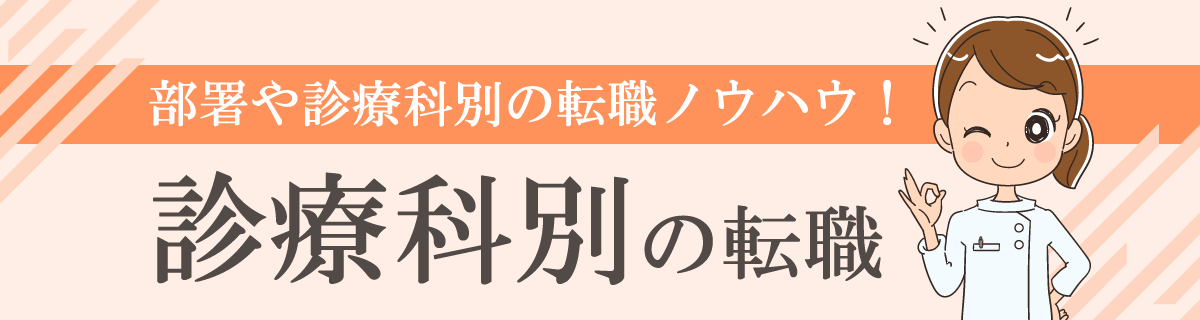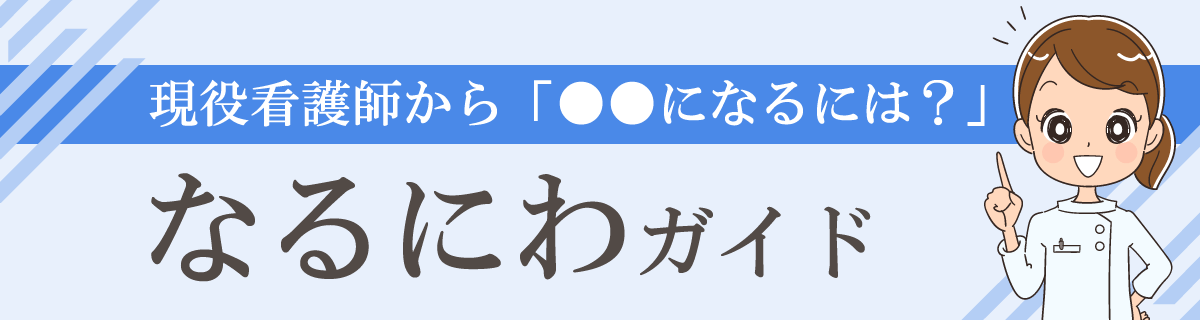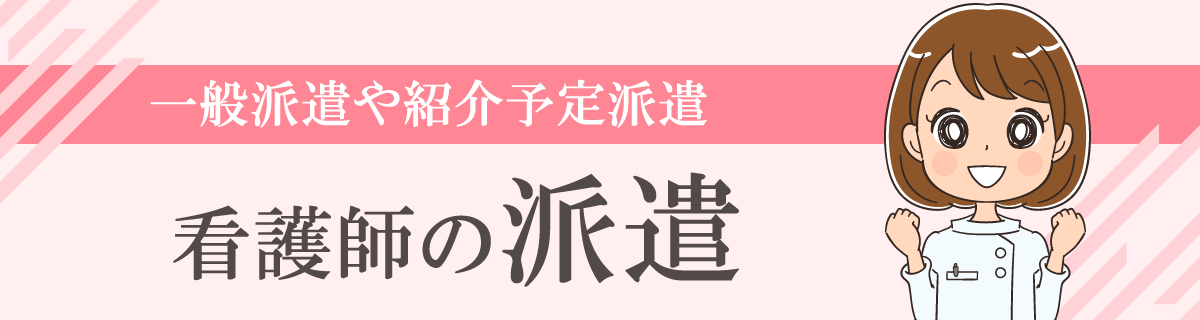看護師の面接で質問と回答例30個(転職編+解説付き)
看護師の転職活動では、病院やクリニックなど医療機関での面接が合否を大きく左右します。頭では分かっていても、いざ面接官を前にすると緊張して言葉に詰まってしまったり、聞かれたことにうまく答えられなかったりと、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、看護師の転職面接で聞かれる質問にはある程度「パターン」があります。よくある質問とその意図を理解し、自分の言葉で答えられるように準備しておけば、過度に緊張することなく、自分の強みや仕事への意欲をしっかりと伝えやすくなります。
本番の面接では、次のポイントを意識して話すようにしましょう。
- 質問に対しては、まず結論から簡潔に伝えること
- 聞かれた内容にきちんと答え、余計なことをダラダラ話さないこと
- 相手の話を聞くときは、軽くうなずきながら目を見て聞くこと
- 履歴書・職務経歴書の内容と矛盾しないよう、一貫性を持って話すこと
面接は「正解を当てる場」ではなく、「一緒に働きたいと思ってもらえるか」を見られる場です。看護スキルやこれまでの経験だけでなく、仕事への姿勢やコミュニケーションの取り方も評価されますので、表情や声のトーンも意識しながら、落ち着いてハキハキと回答していきましょう。
このページでは、看護師の転職面接でよく聞かれる17の想定質問について、「質問の意図」「好印象につながる答え方のポイント」「具体的な回答例」をセットで解説します。自分の状況に置き換えながら読み進め、面接本番に備えておきましょう。
執筆・監修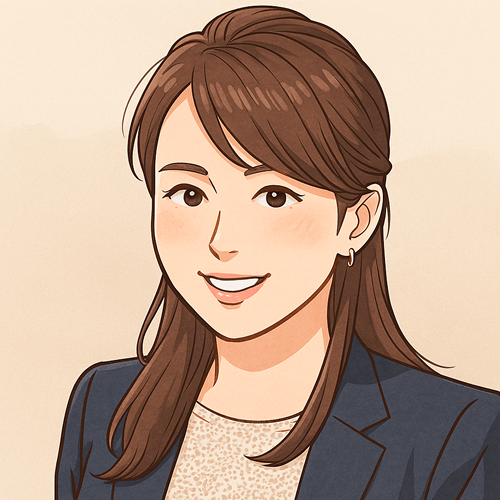
当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。

- エリア:神奈川県在住
- 保有資格:看護師、がん看護専門看護師、消化器内視鏡技師、心理相談員
- 経歴:がん専門病院、総合病院、クリニック、総合病院、訪問診療クリニック
- 専門分野:消化器内科、透析室、内視鏡室、放射線治療室、泌尿器科
看護師をして20年以上になります。外来・病棟・検査室・クリニックなど、いろいろな場所での業務を経験しました。ですが、一時は看護師をやめようと思ったほど、心身共に追い詰められた時期もあります。現在は、看護師も続けつつ、ライターやカウンセラーとしても活動しています。
看護師転職面接30の想定質問と回答例
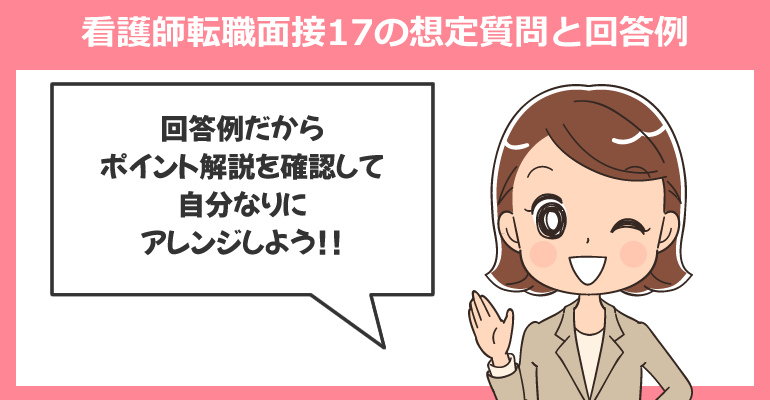
ここからは、看護師の転職面接でよく聞かれる17の質問について、質問の意図・答え方のポイント・具体的な回答例をセットで整理していきます。まずは一通り読みながら「自分の経歴や志望先ならどう言い換えられるか」をイメージし、そのうえで実際に紙やメモアプリに自分の言葉で書き起こしてみると、本番でもスムーズに話しやすくなります。
なお、ここで紹介する回答例はあくまで「型」の参考です。丸暗記するのではなく、あなたの経験・強み・希望する働き方に合わせてアレンジし、面接官に「一緒に働きたい」と感じてもらえるようなオリジナルの回答に仕上げていきましょう。
1.志望動機は何ですか?
回答例文1:急性期経験から地域医療へ
「これまで急性期病棟で術後管理や急変対応を中心に経験してきましたが、患者の退院後の生活まで支援できる看護にも関わりたいと感じるようになりました。御院は急性期から在宅まで一貫した地域医療に注力されており、自分の経験を活かしながら支援の幅を広げられる環境だと考え、志望いたしました。」
回答例文2:クリニック志望(継続的な関わり)
「病棟勤務では患者と関われる時間が限られることが多く、より長期的に寄り添う看護を学びたいと感じるようになりました。生活指導や予防医療など、患者の日常に近い距離で支援できるクリニックの看護に魅力を感じ、御院を志望いたしました。」
回答例文3:ブランク明け・子育てとの両立
「出産と子育てのため一度現場を離れていましたが、再び看護に戻るにあたり、教育・サポート体制が整った職場で働きたいと考えていました。御院は復職支援に力を入れておられ、段階的に学び直しができる点に安心感を持ち、志望いたしました。」
解説・ポイント
志望動機では、以下の3点が特に評価されます。
- 応募先の特徴を理解しているか
- 自身の経験と応募先の強みが結びついているか
- 待遇目的ではなく明確な理由があるか
「応募先固有の特徴」を入れると説得力が大きく上がります。(例:地域包括ケア、在宅支援、専門外来、教育体制など)
2.なぜ転職しようと思ったのですか?
回答例文1:キャリアアップ(新たな分野へ挑戦)
「急性期で幅広い症例を担当し多くを学びましたが、今後は慢性期や地域医療など、患者と長期的に関わる看護にも挑戦したいと考えるようになりました。御院は生活背景も含めた包括的な支援に力を入れておられ、自分の学びたい看護が実践できると感じています。」
回答例文2:働き方改善(無理なく長期的に働きたい)
「生活環境の変化により働き方を見直す必要があり、無理なく長期的に働ける環境を求めて転職を考えました。御院は勤務体制が整い、チームで連携しながら業務に取り組める点に魅力を感じています。自身の生活と仕事のバランスを保ちながら、患者にしっかり向き合いたいと思っています。」
回答例文3:クリニック志望(継続看護をしたい)
「病棟では入退院のサイクルが早く、一人の患者と長く関わることが難しい場面もありました。生活習慣や体調の変化を踏まえながら継続的な看護を提供できる点に魅力を感じ、クリニックでの勤務を希望するようになりました。」
解説・ポイント
転職理由は、前向きな理由であることが重要です。
- キャリアアップしたい
- 違う領域を学びたい
- 働き方を見直したい
- 患者と長く関わりたい
「前職の不満」ではなく「今後どうなりたいか」で語ると高評価につながります。
3.退職理由は何ですか?
回答例文1:キャリアアップ(高度医療への挑戦)
「外科病棟で周術期管理や急変対応を学んできましたが、より高度な救急看護に挑戦したいと考え退職いたしました。新しい環境で判断力や医療知識をさらに深めたいと思っています。」
回答例文2:転居・転勤
「配偶者の転勤に伴い通勤が困難になったため前職を退職いたしました。現在は生活基盤が整い、安定して勤務できる環境です。」
回答例文3:病気・休養明け
「体調不良により休養が必要となり退職いたしましたが、現在は医師の判断もあり業務に支障のない状態まで回復しています。これまでの経験を活かし、改めて看護に向き合いたいと考えています。」
解説・ポイント
退職理由は面接官が最も慎重に確認します。
- トラブル退職ではないか
- 説明が矛盾していないか
- 現在は安定して働けるか
ネガティブな話題は避け、以下のように話すことがポイントです。
- 前職経験を肯定的に述べる
- 退職理由は簡潔に事実のみ述べる
- 現在は支障なく勤務可能であることを明言する
| 転居・転勤の場合 | 事実を簡潔に述べ、現在は勤務が安定してできることをセットで伝える |
|---|---|
| 介護・病気・育児の場合 | 現在は勤務に支障がないことを必ず添える |
| ネガティブな転職理由の場合 | 前職の批判は避け、キャリア方向性の転換として前向きに説明する |
4.職務経験・職務内容を教えてください
回答例文1:急性期病棟での経験
「〇病院の腹部外科病棟に〇年勤務し、周術期看護とストマ管理を中心に経験してきました。術前・術後の全身管理や疼痛コントロールに携わるなかで、急変時対応や多職種連携の重要性を学びました。〇年目からはプリセプターとして新人指導を担当し、病棟全体の情報共有やチーム医療の推進に関わってきました。」
回答例文2:外来・クリニックでの経験
「これまで内科系クリニックの外来に勤務し、診察介助、採血や点滴、内視鏡検査の準備・介助、健康診断対応などを行ってきました。限られた時間の中で患者の訴えを整理し、医師に必要な情報を的確に伝えることを心がけてきました。また、生活習慣病の患者には継続した支援が大切だと感じ、検査結果の説明やセルフケア指導にも力を入れてきました。」
回答例文3:訪問看護・在宅分野での経験
「訪問看護ステーションに勤務し、がん終末期や慢性心不全などの患者宅を1日〇件程度訪問してきました。バイタルチェックや症状観察、服薬管理だけでなく、家族へのケアや多職種との情報共有も担当してきました。状態変化の早期発見や、最期まで自宅で過ごしたいという希望を尊重できるよう、医師やケアマネジャーと連携しながら支援してきました。」
解説・ポイント
面接官は履歴書を見たうえで、この質問を通して「具体的にどのような業務をしてきたのか」「どの場面で強みが発揮される看護師なのか」を確認しようとしています。
そのため、以下の点を意識してまとめておくと伝わりやすくなります。
- 勤務していた施設の種類・診療科・病棟か外来か
- 日常的に担当していた主な業務内容
- 力を入れてきた看護や役割(プリセプター、リーダー業務など)
職歴が複数ある場合は、全てを細かく話そうとせず、直近の職場や応募先に関連性が高い経験を中心に、エピソードを交えて説明すると良い印象につながります。また、履歴書に書いている内容と大きなズレがないよう、事前に話す内容を整理しておくことも大切です。
5.就職後、何をやっていきたいですか?
回答例文1:専門性を深めたい(内視鏡・急性期など)
「これまで外来勤務の中で内視鏡業務に携わる機会があり、検査前後の管理や鎮静時の観察など、より専門的な知識を深めたいと考えてきました。御院の内視鏡室は症例数も多く、学べる環境が整っていると感じています。入職後はまず業務の流れを確実に習得し、将来的には内視鏡技師資格の取得にも挑戦し、患者の安全と安心を支える役割を担いたいと考えています。」
回答例文2:患者とのコミュニケーションを大切にしたい
「私はこれまで、患者の不安をできるだけ軽減できるよう、一つひとつの説明を丁寧に行うことを心がけてきました。忙しい状況でも“患者の理解度を確認する余白”を作ることの重要性を強く感じています。御院でも、患者の気持ちに寄り添いながら、安心して治療を受けてもらえるような看護を実践していきたいと考えています。また、患者とのコミュニケーションを重視する文化が根付いている点に魅力を感じています。」
回答例文3:在宅移行支援や退院支援に関わりたい
「これまで病棟で勤務する中で、退院支援や在宅への橋渡しの重要性を強く実感してきました。退院前カンファレンスや家族支援に関わる機会を通して、 “退院後の生活を見据えた看護” を提供できる看護師になりたいと思うようになりました。御院では地域連携や多職種協働を重視されているため、自分の経験を活かしつつ、より広い視野で患者の生活支援に携わりたいと考えています。」
回答例文4:ブランク明けとして基礎を丁寧に積み直したい
「子育てによるブランクがあるため、まずは基本的な看護技術と業務の流れを丁寧に習得し、確実に業務がこなせるようになりたいと考えています。御院は教育・研修制度が整っており、段階的にスキルを磨ける点に魅力を感じています。焦らず一つひとつ積み上げながら、患者にとって安心できる存在になれるよう努力したいです。」
解説・ポイント
この質問では、面接官は以下を確認しています。
- 応募者の将来像が明確かどうか
- 自分の経験と応募先の特徴が結びついているか
- 過度な希望や「〇〇病棟でなければ嫌」などの強すぎる主張がないか
最も良い回答構成は次の3つです。
- これまでの経験で興味を持った点を述べる
- 応募先で学びたい・挑戦したい内容を述べる
- そのために努力する姿勢を言語化する
抽象的な「どんな部署でも頑張ります」ではなく、「自分の経験 → そこから芽生えた興味 → 応募先とマッチしている理由」を伝えることで、面接官に「この人が働く姿」が具体的に思い描いてもらいやすくなります。
6.勤務はいつから可能ですか?
回答例文1:現在勤務中(調整が必要)
「現在の職場に在職中のため、引継ぎや退職手続きの関係上、〇月からの入職を予定しています。できるだけ早く勤務開始できるよう調整したいと考えており、内定をいただいた段階で上司へ正式に退職の申し出を行い、改めて具体的な入職日をお伝えいたします。」
回答例文2:離職中(すぐに勤務可能)
「現在は離職中のため、御院のご都合に合わせて勤務を開始することが可能です。必要な手続きや準備があれば、すぐに対応できますので、お申しつけください。」
回答例文3:ブランク明け(生活調整が必要)
「子育てとの両立のため一度離職していましたが、現在は保育環境も整っており、〇月から常勤として勤務を開始できます。勤務開始後、業務に支障が出ないよう、家庭側のサポート体制も整えております。」
回答例文4:非常勤から常勤へ切り替えたい場合
「現在は非常勤として勤務していますが、シフト調整がしやすいため、〇月初旬から御院での勤務を開始可能です。常勤として働ける環境を整えており、早期に業務へ慣れ、できる限り早く戦力になれるよう努めます。」
解説・ポイント
勤務開始日は、採用側が「いつから現場のシフトに組み込めるか」を判断する重要項目です。面接官は次の点を確認しています。
- 入職可能時期が具体的かどうか
- 在職中の場合、退職手続きを適切に進める意思があるか
- 家庭や体調面で安定して働ける状況か
回答時のポイントは以下の通りです。
- 「◯月から可能です」と月単位で明確に述べる
- その時期になる理由(引継ぎ・家庭調整など)を簡潔に添える
- 前向きに早く働きたい姿勢を示す
- 在職中の場合は“内定後に正式調整する”ことを明示する
中途採用では以下が目安です。さらに詳しくは「看護師の転職面接で「いつから働けるか」を聞かれた場合のベスト回答は?」を確認してください。
| 入職時期 | 原則:内定後1〜3ヶ月以内が一般的 |
|---|---|
| 内定後の返答 | 2〜3日以内が好印象 |
早めに勤務してほしいクリニックや病棟では、 明確で調整可能な日程を示すほど評価が高くなります。
※看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)を利用している場合は退職相談も可能な場合があります。
7.看護で大切にしていることを教えてください
回答例文1:患者の尊厳を守る看護
「私は、入院生活によって患者の生活リズムや自立性が制限される場面を多く経験してきました。そのため、患者の尊厳を守り、その人らしさを大切にした関わりを常に意識しています。検査や処置の説明では、患者の理解度を確認しながら不安を取り除けるよう努め、自分の価値観を押しつけずに寄り添う姿勢を大切にしています。」
回答例文2:安全性を最優先にした看護
「どれほど忙しい状況であっても、確認作業を省略しないことを最も大切にしています。確認不足はインシデントにつながり、患者の安全を損ねる可能性があります。私は指差し確認や、医療者同士のダブルチェックを徹底し、チームとして安全を守る姿勢を心がけてきました。これまでの勤務でも、ミス防止への意識を徹底し、チーム内でも安心して業務を任せてもらえる環境づくりに努めてきました。」
回答例文3:多職種連携を重視した看護
「患者の状態や生活背景は一人の看護師だけでは把握しきれないことが多いため、医師、リハビリ、薬剤師、ソーシャルワーカーなど多職種と連携し、同じ方向に向かって支援することを大切にしています。私はカンファレンスや日々の情報共有を通して、チームとしての統一した支援を行えるよう意識してきました。多職種の視点を学ぶことで、自分自身の看護観も広がっていくと感じています。」
回答例文4:ブランク明けとしての丁寧な看護
「ブランクがある分、焦らず一つひとつ丁寧に確認しながら業務に取り組むことを大切にしています。患者の小さな変化や不安の表情に気付けるよう、観察を怠らないこと、自分が迷った時は必ず先輩に相談することを徹底しています。丁寧さと誠実さを強みに、患者に安心していただける看護を心がけています。」
解説・ポイント
この質問は、面接官が「人柄」「価値観」「コミュニケーション力」を把握するために必ず聞く重要質問です。
以下の観点で回答すると、より説得力が増します。
- 自身の経験から得た“看護観”が語れているか
- 抽象的な理想論ではなく、具体的な行動につながっているか
- 応募先の看護方針・理念と矛盾していないか
特に、応募先の理念に「寄り添う看護」「チーム医療」「地域に根ざした看護」などのキーワードがある場合、自分の看護観とリンクする表現を使うと評価が高くなります。
また、複雑な用語や抽象的な表現を多用せず、 「私は〇〇を大切にしています。その理由は△△という経験があったからです」 というシンプルな構成が最も伝わりやすいです。
8.インシデントの経験はありますか?
回答例文1:患者取り違え未遂(外来)
「外来で患者の呼び入れを行った際、苗字だけで呼んでしまい、別の患者を案内しそうになったことがあります。説明を始めてすぐに違和感を覚えて確認し、誤りに気付きました。すぐに謝罪と報告を行い、その後はフルネームと生年月日のダブルチェックを徹底しています。同時に、声かけ方法を外来看護師間で統一し、同じミスを起こさない環境づくりにも取り組みました。」
回答例文2:薬剤投与量の誤りに気づいたケース(病棟)
「点滴準備を行った際、オーダーと処方量に差異があることに自分で気付き、投与前に師長へ報告し、医師確認のもと訂正されました。投与前に気付けたことで事故には至りませんでしたが、以降は“自分で声に出して読む”“同僚にも確認してもらう”など、複数の確認方法を取り入れるようにしています。」
回答例文3:転倒リスクに関するヒヤリハット(病棟)
「夜間巡視の際に患者がベッド端に座り不安定な姿勢になっている場面に遭遇しました。事前の環境調整が不十分だったことが原因だと感じ、転倒には繋がりませんでしたが反省点となりました。以降はベッド周囲の環境整備を徹底し、ADLを踏まえたリスク評価をチームで共有する体制を強化しました。」
回答例文4:クリニックでの検査準備ミス
「クリニック勤務時、検査前に必要な器具の準備漏れがあり、患者を待たせてしまいそうになった経験があります。すぐに先輩へ報告して対応を行い、手順をチェックリスト化して以降はミスなく準備が行えるようにしました。小さなミスでも患者の安心感に影響するため、準備段階の細かな確認の重要性を強く学びました。」
解説・ポイント
この質問で面接官が確認したいのは 「問題をどう受け止め、どのように改善したか」 です。インシデントの内容そのものよりも、以下を重視しています。
- 冷静に状況を振り返れているか
- 報告・相談が適切にできているか
- 同じミスを防ぐための工夫ができているか
インシデントは医療現場でゼロにはできません。大切なのは、以下の構成で話すことです。
- どんな場面で何が起きたか(簡潔に)
- どう対処したか(報告・相談・謝罪など)
- 今後同じことを防ぐための改善策
また、重大事故につながるケースは避け、「未然に防げた」「その後に改善行動を取った」というエピソードを選ぶことが最も好印象につながります。
9.自己PRをお願いします
回答例文1:専門性×学習意欲(呼吸器・内科系)
「私はこれまで総合病院の内科病棟で勤務し、特に呼吸器疾患の患者を担当する機会が多くありました。人工呼吸器管理に興味を持ち、呼吸療法認定士の資格も取得しました。学んだ知識を院内勉強会で共有したり、新人指導に活かすなど、チーム全体の知識向上にも貢献してきました。今後も学びを深めながら、患者の安全と安心に寄り添える看護を実践していきたいと考えています。」
回答例文2:継続看護・粘り強さが強み
「私の強みは“粘り強く支援を続けられること”です。慢性疾患の患者と関わる中で、病気への不安や生活習慣の見直しなど、時間をかけて向き合う必要性を強く感じてきました。患者の生活背景を理解し、その方に合わせた言葉かけを意識することで、治療への意欲を引き出す関わりができたと実感する場面も多くありました。継続的な支援が求められる職場でも、この強みを活かしていきたいです。」
回答例文3:安全重視・確認作業の徹底
「私は“どれだけ忙しくても確認作業を絶対に省略しないこと”を大切にしています。確認不足はインシデントにつながり、患者やチームに大きな影響を与えるためです。指差し確認・声出し確認を徹底し、疑問点は必ず周囲に相談してから進めてきました。結果として、大きな事故を起こすことなく、安心して業務を任せてもらえる存在として評価いただけることが増えました。今後も安全を第一に行動していきたいと考えています。」
回答例文4:ブランク明けでも誠実さを武器に
「子育てによるブランクで業務に不安があった時期もありますが、その分、丁寧な確認や学び直しを積極的に行う姿勢を大切にしてきました。復職後は“丁寧かつ誠実な対応”を評価され、患者からの相談やフォローを任されることも増えました。ブランクがあるからこそ、わからないことを素直に聞く姿勢や、慎重に進める姿勢を強みに変えていきたいと考えています。」
解説・ポイント
自己PRでは、面接官は以下の視点で判断しています。
- 自分の強みを客観的に理解できているか
- その強みが「看護業務でどう活かされるか」を言語化できているか
- 話が具体的で、実際の行動につながっているか
特に効果的な構成は次の3つです。
- 自分の強み(1つに絞る)
- 強みが発揮された具体的エピソード
- 今後どう活かすか
抽象的な表現(例:「明るい性格です」「真面目に頑張ります」)よりも、実際の行動や成果を交えた説明が面接官の心に残りやすく、高評価につながります。
10.どんな時にストレスを感じますか?
回答例文1:業務が重なった時でも優先順位で対応
「複数の業務が一度に重なった時にストレスを感じることがありますが、優先順位を整理して一つずつ確実に進めるようにしています。状況が立て込んだ際こそ焦らないことを意識し、必要な場合は周囲に相談しながら業務を行うことで落ち着いて対処できるよう努めています。」
回答例文2:急変時の緊張感を前向きなエネルギーに
「急変対応が続く時は緊張感からストレスを感じることがあります。ただ、その場で慌てないよう、日頃から勉強会への参加やマニュアルの確認を行い、想定外の状況にも冷静に対応できるよう準備しています。緊張は完全にはゼロにできませんが、事前準備とチーム連携で軽減できると考えています。」
回答例文3:患者対応が難しい時のストレスとの向き合い方
「患者の不安や怒りが強く、思いをうまく受け止められない時にストレスを感じることがあります。そのような場面では、一度気持ちを切り替え、同僚に相談して視点を変えてみることで、より良い対応につなげるようにしています。患者の背景を理解しようとする姿勢を大切にし、冷静に関われるよう工夫しています。」
回答例文4:経験が浅い時の不安を行動でカバー
「経験が浅い分、処置や判断に迷う場面でストレスを感じることがありました。ただ、その不安を改善するために、手技の復習や先輩への確認を徹底し、知識と経験で解消しています。分からないことをそのままにせず、必ず確認する姿勢を持つことで、安心して業務に取り組めるようになりました。」
解説・ポイント
この質問で面接官が見ているのは、ストレスそのものではなく「ストレスとの向き合い方」です。
チェックされているポイントは以下の通りです。
- ストレスを抱えた時にどのように対処しているか
- 周囲に相談する姿勢や、自己管理ができているか
- ストレスで仕事に支障が出るタイプではないか
避けるべきNG回答は以下の通りです。
- 「忙しいとストレスです」だけで終わる(改善策がない)
- 「注意されると落ち込みます」など業務支障を連想させる内容
- 特定の人物や環境を批判する言い方
最も評価されるのは、「ストレスを感じる場面を冷静に把握し、その上で対処法を持っている」という姿勢です。
これは看護業務における自己管理能力の高さとして、面接官から高く評価されます。
11.ストレス解消法は何ですか?
回答例文1:気持ちの切り替えを習慣化
「嫌なことがあっても、職場を出たら気持ちを切り替えることを意識しています。意識的に仕事のことを考えない時間を作ることで、翌日には冷静に業務に向き合えるようになります。仕事とプライベートを分けることで、ストレスを抱え込まないように工夫しています。」
回答例文2:運動や身体を動かすことで発散
「以前から身体を動かすことが好きなので、休日はジムやランニングで汗を流すようにしています。運動すると気持ちがすっきりし、考えすぎてしまう癖も改善されます。心身のリフレッシュに役立っているため、自然とポジティブに業務へ向かえるようになります。」
回答例文3:趣味の時間でリラックスする
「家では音楽を聴いたり、好きなドラマを見たりして、自分の時間を大切にしています。特に疲れが溜まっている時は、好きなものに触れることで、心が落ち着き、翌日の仕事にも前向きに取り組めるようになります。短時間でもリラックスできる方法を持つことがストレス解消につながっています。」
回答例文4:周囲と話して気持ちを整理する
「ストレスを感じた時は、一度自分の気持ちを整理するために、信頼している同僚や家族に話を聞いてもらうようにしています。話すことで気持ちが軽くなり、冷静に状況を振り返ることができます。抱え込まずに相談することで、より良い解決策につながることも多いと感じています。」
解説・ポイント
この質問は、面接官が 「ストレス耐性」 と 「セルフケア能力」 を見るためのものです。
特に以下が重視されます。
- 自分の状態を客観的に把握できているか
- ストレスを溜め込まず適切に対処できるか
- 仕事に支障が出ないよう工夫しているか
好印象を与えるポイントは次の通りです。
- ストレスは誰にでもあるという前提で、前向きな対処法を示す
- 健康的で現実的な方法(運動・趣味・気分転換)を挙げる
- 「翌日には業務へ前向きに取り組める」など、仕事への影響が少ないことを示す
NGなのは以下です。
- 「ストレスはありません」と言い切る
- 飲酒に依存する内容
- 他者批判につながる解消法
ストレス解消法を具体的に語れると、面接官に「自己管理ができる看護師」という印象を与えられます。
12.看護の良い・大変なところを挙げて下さい
回答例文1:やりがいを感じる瞬間と、精神的負荷の大きさ
「看護の良いところは、患者と直接関わり、その方が少しずつ回復していく姿に触れられる点だと感じています。『ありがとう』という言葉をいただく瞬間は、何よりのやりがいになります。一方で、大変なところは、命に関わる判断や精神的負担の大きい場面があることです。そうした時でも、チームで連携しながら患者を支える姿勢を忘れないように心がけています。」
回答例文2:継続看護の喜びと、体力面のハードさ
「患者の小さな変化に気付き、長期的に関われる看護の魅力を強く感じています。退院された後に外来でお会いできたり、感謝の言葉をいただけたりすることで、支援がつながっていることを実感できます。一方、夜勤や重症患者のケアなど体力的に厳しい場面も多く、常に体調管理が求められる点は大変だと感じます。休むべき時はしっかり休み、長く続けられる働き方を意識しています。」
回答例文3:チーム医療の楽しさと、コミュニケーションの難しさ
「看護の良いところは、医師・薬剤師・リハビリ・ソーシャルワーカーなど多職種と協力しながら、チームとして患者を支えられる点です。それぞれの専門性を学び合う場面が多く、自分の成長にもつながります。その反面、考え方の違いから意見が合わないこともあり、コミュニケーションの難しさを感じることもあります。ただ、その都度“患者にとって何が一番良いか”を共通の軸にすることで、解決できると実感しています。」
回答例文4:ブランク復職で感じた良さと課題
「ブランクからの復職で不安もありましたが、患者の気持ちに寄り添いながら支える看護の良さを改めて感じています。一方で、医療の進歩や新人教育の体制が変化していたため、覚え直すことの多さに大変さを感じることもありました。それでも、周囲のサポートを受けながら着実に学び直すことで、看護の面白さを再確認できました。」
解説・ポイント
この質問は、面接官が「看護の本質をどれだけ理解しているか」「仕事への向き合い方が現実的か」を確認するためのものです。
特に見られるポイントは以下の通りです。
- 良い点と大変な点をバランスよく理解できているか
- 大変な点に対して、どう乗り越えているかを説明できるか
- 応募者の価値観が職場の雰囲気と合いそうか
最も効果的な構成は次の3つです。
- 看護の良さ(やりがい)
- 看護の大変さ(現実的な課題)
- その課題に対する自分の工夫・姿勢
良いところだけを話すと現実を知らない印象になり、大変なところだけを話すとネガティブな印象になります。
両方を織り交ぜ、そのうえで前向きな姿勢を示すことが最も好印象です。
13.医療ニュースで何に興味を持ちましたか?
回答例文1:地域包括ケア・在宅医療に関するニュース
「最近では“地域包括ケア”に関するニュースに特に関心を持っています。急性期から在宅まで切れ目なく支援する体制が求められる中で、自分の看護観とも重なる部分が多く、もっと深く学びたいと感じています。まだ十分に理解できていない部分もありますが、業務に活かせるように今後も情報収集を続けたいと思っています。」
回答例文2:感染症対策・医療安全に関するトピック
「感染症対策や医療安全に関するニュースをよくチェックしています。特に近年は院内感染の事例や対応策などが報道されることが増え、日常の看護業務にも直結する内容だと感じています。自分の職場での取り組みと照らし合わせながら、より安全な医療提供につながるヒントを得るよう心がけています。」
回答例文3:高齢者医療・認知症ケア関連のニュース
「高齢者医療や認知症ケアに関するニュースに関心を持っています。現場でも認知症の患者に関わる機会が増えており、コミュニケーション方法や家族支援のあり方など、学びが必要だと感じています。新しいケア方法や地域での取り組みを知ることで、日頃の看護に活かせると考えています。」
回答例文4:働き方改革・看護配置の見直し
「看護師の働き方改革や看護配置基準の見直しに関する報道にも注目しています。人員配置や業務負担の軽減が議論される中で、現場で働く看護師としても重要なテーマだと感じています。制度の変化を理解することで、職場全体の働き方の改善にもつなげられるのではないかと思っています。」
解説・ポイント
この質問は、面接官が「日頃から医療情報に関心を持っているか」を確認するためのものです。特に見られているポイントは以下です。
- 医療従事者として最低限の情報収集ができているか
- ニュースを自分の業務や関心領域と結びつけて考えられているか
- 「今後学びたい」という前向きな姿勢があるか
回答のコツは次の3つです。
- ニュースのテーマを具体的に挙げる
- なぜそれに興味を持ったのか理由を述べる
- 今後どのように学びたいかを添える
注意点として、専門的すぎる内容を語りすぎる・うろ覚えで話すのは逆効果です。
面接官から深掘りされた時に回答できなくなるため、「詳しく学びたい」「まだ理解が浅い部分もある」といった謙虚さを含めると好印象を与えられます。
14.採血や注射はできますか?
回答例文1:経験豊富で自信あり(病棟・外来)
「これまで病棟および外来で採血・点滴・静注を数多く経験しており、基本的な技術には自信があります。患者の血管の状態に応じて針の選択や声かけを工夫するなど、安全性と苦痛の軽減を意識してきました。御院で勤務する際にも、まずは施設のルールややり方を確認し、正確に実践したいと考えています。」
回答例文2:経験あり・ブランクがあるが問題なく再習得可
「以前の職場で採血や点滴業務を担当していましたが、ブランク期間があるため、最初は指導を受けながら確実に手技を思い出していきたいと考えています。基礎は身についているため、御院のやり方を確認しながら、早期に独り立ちできるよう努めます。」
回答例文3:経験は少ないが積極的に習得する姿勢を示す
「採血や注射の経験は少ないですが、現職では処置に立ち会いながら手順や注意点を学んでいました。御院で勤務する際には、先輩から指導を受けながら慎重に練習し、早く業務に貢献できるよう努力していきたいと考えています。安全性を最優先に、正確に習得したいと思っています。」
回答例文4:クリニック勤務を見据えた前向きな姿勢
「クリニックでは採血や注射の機会が多いことを理解しており、業務に必要な技術を積極的に身につけたいと考えています。これまでも先輩の処置を見学し、手順を復習するなど準備をしてきました。御院の基準に沿って安全に実践できるよう、丁寧に学んでいく所存です。」
解説・ポイント
この質問で面接官が見ているのは、「技術の有無」ではなく「技術に対する姿勢・安全への意識」です。特に以下の点が評価されます。
- 安全性への配慮(確認・声かけ・判断)
- できる範囲とできない範囲を正直に伝えられるか
- ブランクがあっても“学ぶ姿勢”を示せるか
- クリニック・病棟など職場の特徴を理解しているか
以下のような姿勢はマイナス評価となるため注意が必要です。
- できないのに「できます」と過剰に言い切る
- 反対に「苦手です」とネガティブに言い切る
- 安全性より“スピード”を優先する内容
最も評価されるのは「安全を確保しながら、必要に応じて学ぶ意欲を持っている」というバランスの取れた回答です。
15.職種・年齢を問わずチームを組めますか?
回答例文1:年齢差のあるチームでも柔軟に連携
「これまで幅広い年齢層のスタッフと働いてきましたが、年齢に関係なく互いの強みを理解することが大切だと感じています。自分より若いスタッフから学ぶことも多く、意見を聞き入れながらチームとして良い看護を提供できるよう努めてきました。御院でも、相手の立場を尊重しながら協力したいと考えています。」
回答例文2:他職種と協働しながら役割分担を意識
「医師・薬剤師・リハビリスタッフなど、多職種と協働しながら業務を進める経験を積んできました。お互いの専門性が異なるからこそ、情報共有や相談をこまめに行うことで、統一したケアを実践できると考えています。役割分担を意識しつつ、必要な時には遠慮なく意見交換できる関係作りを大切にしています。」
回答例文3:新しいチームでも早く溶け込む工夫
「新しいチームに入る際は、まず“相手を知る姿勢”を意識しています。わからないことは素直に聞き、自分ができることは積極的に声を出して協力することで、円滑にコミュニケーションが取れるようになります。これまで異動先でも早くチームに馴染めた経験があり、御院でも同じ姿勢で取り組んでいきたいと考えています。」
回答例文4:ブランク後でも協調性を大切に
「復職後は特に周囲のサポートを受けながら業務に取り組むことが多く、協調性の重要性を強く感じました。指導してくれるスタッフに感謝の気持ちを持ちながら、分からない部分を曖昧にせず相談することで信頼関係を築いてきました。これからも、チームの一員として役割を果たせるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけたいと思っています。」
解説・ポイント
この質問では、面接官は「チームに馴染めるか」「コミュニケーションに問題がないか」を慎重にチェックします。特に以下の点が重視されます。
- 年齢差や立場の違いに柔軟に対応できるか
- 自分の意見を押しつけず、相手を尊重できるか
- 多職種連携を理解しているか
- 協調性・相談しやすさがあるか
NGとされやすい回答は以下です。
- 「基本的に一人で進めるのが好きです」
- 「年上の人と合わないことがあります」
- 過去のチームトラブルを詳細に語る
最も評価される回答は、相手を尊重する姿勢と自分からコミュニケーションを取る行動がセットで示されている回答です。応募先がどのような職種構成か理解していれば、より具体的な回答が可能になります。
16.看護師になった理由はなんですか?
回答例文1:家族の入院をきっかけに看護の道へ
「中学生の頃、祖父が入院した際に、担当の看護師が常に声をかけ、家族にも丁寧に説明してくれる姿に強く憧れを持ちました。その看護師のおかげで祖父も家族も安心して治療に向き合うことができ、私自身も心が救われた経験があります。そのことがきっかけで、“自分も誰かの支えになれる仕事がしたい”と思い、看護師を志しました。」
回答例文2:医療・人体への興味から専門職を選択
「学生の頃から人体の仕組みや医療分野に興味があり、学ぶほど奥深さを感じるようになりました。進路を考えた際に、専門知識を実践に活かしながら、人の役に立てる職業として看護師に魅力を感じました。実際に働く中で、患者の回復を支える楽しさや、知識が直接役立つやりがいを強く感じています。」
回答例文3:人と関わり、支える仕事がしたかった
「人と話すことやサポートすることが好きで、“誰かの生活に寄り添って支えられる仕事”に就きたいと考えていました。看護師は、直接患者と関わりながら必要なケアを提供できる点に魅力を感じました。実際に働く中で、声かけひとつで安心してもらえる場面を経験し、この職業を選んで良かったと日々実感しています。」
回答例文4:家族・身近な人の病気を経験して
「身近な家族が病気をした際、医療者の支えで気持ちが前向きになっていく姿を見て、看護師の持つ力の大きさを感じました。その経験から、“患者と家族の心にも寄り添える存在になりたい”と思い看護師を目指しました。現在もその思いを忘れず、患者と家族双方に安心していただける看護を心がけています。」
解説・ポイント
この質問は、「看護観」「人柄」「価値観」を見極めるために必ず問われる重要項目です。面接官が見ているポイントは以下の通りです。
- 看護師を目指した理由が、自分の経験や価値観に基づいているか
- 抽象的でなく、具体的なエピソードが語れているか
- 理想論だけでなく、実際の仕事への理解があるか
好印象になる構成は次の3ステップです。
- 看護師に興味を持ったきっかけ(経験)
- そこから学んだこと・感じたこと
- 現在の看護観や働く姿勢につながっていること
特に、誰かとの関わりがきっかけになっているエピソードは、面接官に「この人なら患者に寄り添える」と伝わりやすいため効果的です。
抽象的な「人の役に立ちたい」だけで終わらず、具体的な過去の経験 → 現在の姿勢の繋がりを示すと、非常に高評価になります。
17.子供がいる場合、支えてくれる人はいますか?
回答例文1:家族のサポート体制が整っている場合
「現在、子供も落ち着いて学校に通っており、急な発熱などの際には夫や両親がサポートできる体制を整えています。学校行事や家庭の事情で事前に休みが必要な場合は、早めにご相談させていただきます。勤務に支障が出ないよう、家族とも連携しながら働ける環境を準備しています。」
回答例文2:パートナー中心のサポート
「パートナーが育児に積極的に関わってくれており、急な対応が必要な場面でも協力できる体制があります。勤務時間帯も調整しやすいため、業務に支障がないよう家庭内での役割分担をしています。必要な連絡は早めに行い、チームに迷惑をかけないよう配慮しながら働きたいと考えています。」
回答例文3:保育園・学童を利用する場合
「保育園と学童を併用しており、勤務時間に合わせて柔軟に預けられる体制を整えています。急な延長保育にも対応できるため、業務に大きな影響が出ないようにしています。家族の協力もあり、勤務に支障のない形で働く準備をしています。」
回答例文4:シングルマザーの場合の前向きな説明
「シングルで子育てをしていますが、実家のサポートを受けながら働く環境を整えています。急な対応が必要な時には、両親や近隣のサポートを利用できるため、勤務に大きな支障はありません。勤務先に迷惑をかけないよう、事前の調整と連絡を徹底して働くことを心がけています。」
解説・ポイント
この質問は、面接官が「急な休みが多くならないか」「勤務に支障が出ないか」を確認するためのものです。特に小規模クリニックや人員が限られている部署では慎重に聞かれます。
面接官が見ているポイントは以下の通りです。
- 急な休みに対応できるサポート体制があるか
- 勤務に支障が出ないよう自ら調整できるか
- チームに迷惑をかけない姿勢があるか
好印象を与える回答のコツは次の3つです。
- 家族・保育園・行政サービスなどサポート体制を具体的に示す
- 勤務に支障が出ないよう工夫していることを伝える
- 学校行事など事前に分かる予定は早めに相談する姿勢を明示する
逆にNGなのは、
- 「急な休みが多いと思います」「サポートが弱いです」など不安を強める発言
- 曖昧な回答で、サポート体制がイメージできない
- 不安や負担を職場に丸投げする印象を与える回答
勤務に影響が出ないよう準備しているという姿勢を見せることで、面接官に安心感を与えることができます。
18.希望する勤務形態(夜勤・オンコール)に問題はありませんか?
「夜勤・オンコールには問題なく対応できます。これまで二交替・三交替のどちらも経験しており、体調管理を含めて働き方のイメージもできています。御院の勤務体制に合わせ、早い段階で業務に慣れ、シフトに安定して入れるよう取り組みたいと考えています。」
「夜勤には問題ありませんが、オンコールに関しては家庭の状況もあるため、最初はご相談しながら調整できればと思っています。ただし、勤務に支障が出ないよう家族のサポート体制を整えているため、段階的にオンコールにも入れるよう調整していく予定です。」
「現在は家庭の事情もあり、夜勤なしの勤務を希望しています。ただ、日勤帯の業務には柔軟に対応でき、早番・遅番も可能です。前職では、患者の処置や診療補助を中心に多様な業務を担当していたため、現場の負担が偏らないように貢献していきたいと考えています。」
解説・ポイント
勤務形態は、採用側にとって最重要項目です。特に次を見られています。
- 応募者の希望とシフト体制がマッチするか
- 夜勤・オンコールに対する“現実的な理解”があるか
- 難しい場合でも、代替案や前向きな姿勢があるか
「可能です/無理です」の二択ではなく、「できる点」「難しい点」「調整の意思」をセットで出すことが最も好印象です。
19.残業や急なシフト変更にはどの程度対応できますか?
「業務の状況によって残業が発生することは理解していますので、基本的には対応可能です。急なシフト変更が必要な場合も、家庭と調整しながら柔軟に対応したいと考えています。チームで協力し合うことの大切さを前職でも実感しているため、業務に支障がないよう行動いたします。」
「子育ての関係で大幅なシフト変更や長時間の残業は難しい場合がありますが、事前に分かる範囲であれば柔軟に調整できます。急な対応が必要な場面でも、家族と協力しながらできる限り負担にならないよう働きたいと考えています。」
「基本的には定時での退勤を心がけていますが、患者の状態や業務の状況に応じた必要な残業には対応できます。前職では“時間内に終わらせる”ことを意識し、優先順位を明確にしながら手際よく業務を進めていました。御院でも効率的な働き方でチームに貢献したいと思っています。」
解説・ポイント
面接官は次の点を見ています。
- 勤務への影響が出ないか
- 周囲と協力する姿勢があるか
- 「できない理由」ではなく「できる工夫」が話せているか
NGなのは「残業は一切できません」「家庭事情でほぼ対応できません」と断定する回答。
一方で、「無理に無理をする」と言う必要もありません。最も評価されるのは、「可能な範囲を明確にし、協力姿勢を示す」回答です。
20.前職の人間関係で意識していたことは何ですか?
「前職では、相手の立場や経験年数を考慮してコミュニケーションを取ることを大切にしていました。忙しい中でも報告・連絡・相談を丁寧に行い、誤解が生まれないよう意識していました。チームが気持ちよく働けることが、結果的に患者のケアにつながると考えています。」
「看護計画の場で意見が分かれることもありましたが、その際は“患者にとって最善かどうか”を軸に話し合う姿勢を意識していました。個人の価値観ではなく、患者中心で考えることで、チームとして良い方向に進められると実感しています。」
「異動で環境が変わった際は、まず自分から話しかけたり、分からないことを素直に聞くようにしていました。自分からコミュニケーションを取ることで、お互いに協力しやすい関係が築けると考えています。御院でも積極的にチームの一員として関わっていきたいと思っています。」
解説・ポイント
面接官が最も警戒しているのは、「人間関係のトラブルを起こすタイプではないか」という点です。
そのため評価されるポイントは以下の通りです:
- 相手を尊重するコミュニケーションができるか
- 自分の意見を押しつけない姿勢があるか
- 価値観の違いを“患者中心”で整理できるか
NGは以下:
- 「前職の人間関係が悪かった」とネガティブに語る
- 特定人物を批判する
- 被害者意識で語る
最も評価されるのは、「協調性」と「自分から溶け込む姿勢」を両方示せる回答です。
21.苦手だと感じる患者や場面はありますか?その際どう対応していますか?
「強い不安や怒りから言葉が荒くなる患者に対して難しさを感じることがあります。ただ、その背景には“病状への不安”や“うまく伝わらないもどかしさ”があると理解し、まずは落ち着いて傾聴することを大切にしています。必要時は同僚と情報共有し、チームで関わることで適切に対応できるよう努めています。」
「認知症の患者は言葉だけでは意図が伝わらない場面があり、最初は難しさを感じていました。現在は、声かけの方法や環境調整を工夫し、何度も同じ説明が必要な場合でも焦らずゆっくり接するようにしています。多職種と連携しながら、その方に合わせた対応をすることで不安を軽減できるよう心がけています。」
「急変対応では緊張やプレッシャーを感じることがありますが、そのために日頃からマニュアルの読み返しや勉強会への参加を続けています。落ち着いて行動できるように、役割分担を確認しながら動くことを意識しています。苦手意識より“準備でカバーする姿勢”を大切にしています。」
解説・ポイント
この質問は「苦手=弱点」を聞いているのではありません。面接官が見たいのは次のポイントです。
- 苦手な場面を客観視できているか
- 課題に対して“改善行動”を取れているか
- チームに悪影響を及ぼすタイプではないか
NGなのは:
- 「特にありません」と答える(自己理解が浅い)
- 患者や家族を批判するような内容
- 改善策を示さない
好印象になるのは、「苦手 → 理由 → 改善行動 → 今後の姿勢」 の流れで話すことです。
22.忙しい時にミスを防ぐために意識していることは何ですか?
「忙しい時こそ、指差し確認や声出し確認を徹底し、情報の思い込みによるミスを防ぐようにしています。特に点滴や投薬は、患者・薬剤・時間の確認を一つずつ丁寧に行ってきました。どんな状況でも“確認を飛ばさない”ことを最も大切にしています。」
「急がなければならない場面では、業務を“緊急度・重要度”で整理して優先順位を明確にしています。また、自分だけで抱え込まず、必要に応じて周囲に声かけし、協力してもらうことでミスを防いでいます。チームで連携することが安全につながると感じています。」
「複数の業務が重なると注意が散漫になるため、投薬や処置など“ミスできない仕事”は他の作業を一旦止め、集中できる時間を確保するようにしています。途中で呼ばれた場合は、作業に戻った際に必ず最初から確認をし直し、安全性を優先するよう徹底しています。」
解説・ポイント
面接官は、「忙しい場面で安全意識が保てるか」を見ています。
特に見られるのは:
- チェック手順の明確さ
- チームに相談する姿勢
- 焦りをコントロールできるか
NGなのは以下です。
- 「特に考えていません」
- 「忙しいと仕方ないと思います」
最も評価されるのは、「具体的な行動レベルのミス防止策」を語れる看護師です。
23.後輩指導やプリセプターの経験はありますか?
「前職でプリセプターを担当し、新人の技術指導だけでなくメンタルフォローも意識して行っていました。できていない点を指摘するだけでなく、“なぜその手順が必要か”を一緒に考えることで理解を深めてもらうよう取り組んでいました。後輩の成長を見守ることにやりがいを感じていました。」
「プリセプター制度はありませんでしたが、OJT担当として複数の後輩の相談に乗る機会が多くありました。困っていることを早めに共有できるよう、声かけや情報交換を意識していました。自分より経験の浅いスタッフが安心して働けるよう、チーム全体でフォローする姿勢を大切にしてきました。」
「これまで明確なプリセプター経験はありませんが、日常業務の中で後輩に手順を説明したり、患者対応のポイントを共有する機会は多くありました。今後は指導にも積極的に関わり、チームの育成にも貢献できる看護師になりたいと考えています。」
解説・ポイント
この質問で面接官が見ているポイントは:
- 教育・指導の経験があるか
- 後輩とどう関わってきたか
- チーム育成に協力する姿勢があるか
特に以下が高評価です:
- 指導の工夫(声かけ・振り返り・メンタルフォロー)
- 説明が「技術だけ」ではなく「理由・背景」まで伝えている
- 指導経験がなくても、前向きな意欲を述べている
NGなのは:
- 「指導は苦手です」「あまり関わりたくありません」
- 後輩の失敗談をネガティブに語る
教育は中途採用では評価されやすいため、「どのような姿勢で指導していたか」を言語化できると非常に強い回答になります。
24.同僚や他職種と意見が合わない時、どう対処しますか?
「意見が分かれる場面では、必ず“患者にとって何が最善か”という軸に立ち返るようにしています。価値観が違うからこそ、情報共有を丁寧に行い、相手の考えを聞いた上で最適な選択肢を一緒に探すよう心がけています。患者中心で考えると、自然と方向性が揃うことが多いと感じています。」
「急いで判断しなければならない場面でも、一度深呼吸して冷静に状況を整理することを意識しています。相手の背景にある考えを理解した上で、自分の意見も落ち着いて伝えると、より建設的な話し合いができると感じています。最終的にはチームで統一した方針で動けるよう意識しています。」
「医師やリハビリなど他職種の方とは視点が異なる場合があるため、まずは“違いを前提”として受け止めるようにしています。その上で、患者の情報を共有し、共通点を探ることで円滑に連携できることが多くあります。必要に応じて調整役に回ることも意識しています。」
解説・ポイント
面接官が確かめたいのは「衝突を避ける能力」ではなく、「建設的にすり合わせる能力」 です。
評価ポイント:
- ネガティブにならず、相手を尊重できるか
- “患者中心”という軸を持てるか
- 感情ではなく、冷静なコミュニケーションができるか
NG回答は:
- 「基本的に合わせます」「反論しません」→ 自主性がない評価
- 「意見が合わないと疲れる」→ メンタルの弱さを疑われる
最も高評価なのは、「相手を理解しつつ、患者中心で方向性を統一致できるタイプ」 です。
25.苦手な看護技術や今後伸ばしたいスキルはありますか?
「急変時の対応は経験が浅いため課題を感じていますが、そのためにマニュアルの確認やシミュレーションへの参加を継続し、少しずつ自信を持てるようになってきました。今後も経験を積みながら、落ち着いて判断できるスキルを身につけたいと考えています。」
「採血が得意とは言えませんが、その分準備や患者への声かけを丁寧に行い、安全性を最優先に取り組んでいます。必要時は先輩に確認をしながら慎重に進めることで、苦手意識を減らしていきたいと思っています。」
「これからは在宅や地域連携に関するスキルも身につけていきたいと考えています。病棟での急性期看護に加えて、退院後の生活を支える視点を学ぶことで、看護の幅を広げたいと思っています。必要に応じて研修や資格取得も検討しています。」
解説・ポイント
この質問は「弱点をどう扱えるか=安全性と成長性」を見ています。
評価されるのは:
- 苦手を正直に認めつつ、改善行動を言語化している
- 苦手が重大な懸念にならないよう説明できている
- 向上心がある
NG回答:
- 「苦手なものはありません」→ 自己理解不足
- 「採血が苦手で…怖くて…」など不安を増幅させる言い方
ベストは、「小さな課題+改善努力+今後の成長意欲」 をセットにすることです。
26.転職先にどのようなサポート体制を期待しますか?
「基本的な業務の流れや施設のルールについて、最初に教えていただける体制があれば十分です。できるだけ早く独り立ちし、チームの一員として力になりたいと考えています。必要以上に手厚い指導を求めるのではなく、自分でも積極的に学んでいく姿勢を大切にしたいと思っています。」
「ブランクがあるため、最初は基本的な手技や業務手順を確認しながら段階的に指導していただけると助かります。ただし、甘えるつもりはなく、自分でも復習や学び直しを行いながら早期に戦力になれるよう努力します。」
「過度なサポートではなく、分からない時に相談しやすい環境があるとありがたいと考えています。前職でも、自分で調べた上で必要な部分だけ先輩に相談するという姿勢を大切にしてきました。御院でも主体的に行動しつつ、必要時にサポートをいただける環境があると嬉しいです。」
解説・ポイント
この質問での評価ポイントは:
- 依存的ではなく、自立した姿勢があるか
- 必要なサポートだけを簡潔に伝えているか
- “教えてもらう側”ではなく“共に働く側”という意識があるか
NG回答:
- 「手厚く全部教えてほしい」→ 依存的・受け身と見られる
- 「特にありません」→ 準備不足・不安視される
ベストな回答は「最低限のサポート+自立した学習意欲」 を示すことです。採用側も、教えれば伸びるタイプを求めています。
27.どのような職場環境だと力を発揮しやすいですか?
「お互いに声をかけ合いながら、困った時は自然とフォローし合える環境だと力を発揮しやすいと感じています。前職でも、情報共有をこまめに行いながら業務を進めることで、安心して患者に向き合うことができました。御院でもチームの一員として、協力しながら働きたいと考えています。」
「業務手順やルールが整理されている環境だと、迷わず行動できるため力を発揮しやすいと感じます。特に医療現場では、一人ひとりの判断が患者の安全に直結するため、情報が共有されていることが重要だと考えています。明確な方針がある中で、自分の役割を確実に果たしたいと考えています。」
「新しい知識や技術を積極的に学べる環境にいると、より意欲的に働けます。前職でも勉強会や研修に参加できる環境だったため、自分の成長につながりました。御院でも学び続けながら、患者のためにより良い看護を提供したいと考えています。」
解説・ポイント
この質問は、「職場との相性(文化・価値観)」 を判断するための重要質問です。
見られるポイントは:
- どのような環境に適応しやすい人か
- 職場のカラーと合いそうか
- あまりにも細かい“こだわり”がないか
NG回答は:
- 「静かで、マイペースに仕事できる職場が良いです」
- 「人との関わりは少ない方が良いです」
ベストは、「協力的・前向き・学習意欲あり」の姿勢 を示す回答です。
28.現在の医療や看護にどんな課題を感じていますか?
「多職種連携が進む一方で、情報共有のタイミングや方法に課題を感じる場面があります。患者の状態変化を共有するタイミングが遅れると、ケアの質にも影響すると感じています。今後はより円滑な情報伝達を意識し、チームとして統一した方向に進めるよう取り組んでいきたいと考えています。」
「新人とベテラン、リーダー業務の有無などによって業務量に偏りが生まれることに課題を感じています。負担が大きい人に業務が集中すると、安全にも影響します。声かけや分担を工夫することで、チーム全体の負担が均一になるよう意識して働いていました。」
「在宅医療が進む中、病院と地域の連携が十分ではないと感じる場面がありました。退院支援に関わる際は、ケアマネジャーや訪問看護との連携を早い段階で図ることで、患者が安心して退院できるよう意識していました。今後は地域全体で支える体制がより求められると感じています。」
解説・ポイント
この質問は、「看護に対して深く考えられるか」を試す中級者〜ベテラン向け質問です。
見られるポイントは:
- 現場を客観視できる視点を持っているか
- 課題=批判ではなく、建設的に語れているか
- 課題に対して自分がどう行動してきたか
NG回答:
- 「人手不足で大変です」「給料が低いことが課題です」
- 愚痴のような内容
最も評価されるのは、「課題 → 自分がしてきた工夫 → 今後どうしたいか」という流れです。
29.長く働くために大切だと思うことは何ですか?
「長く働くためには、心身の健康が最も大切だと感じています。無理をしすぎると、どんなにやりがいがあっても続けられなくなるため、休む時はしっかり休み、オン・オフの切り替えを意識しています。心に余裕があることで、患者にも丁寧に向き合えると実感しています。」
「困った時に相談できる先輩や同僚の存在が、長く働く上で大切だと考えています。一人で抱え込まず、何でも話せる環境があることで、ストレスも溜まりにくくなります。御院でも積極的にコミュニケーションを取りながら、働きやすい関係を築いていきたいと思っています。」
「変化の多い医療現場で長く働くためには、自分自身が学び続ける姿勢を持つことが大切だと考えています。新しい知識を吸収することで自信がつき、業務がより円滑に進むようになります。継続して学び、質の高い看護を提供できるよう努めていきたいです。」
解説・ポイント
この質問は、「定着しやすい人材かどうか」 を見極めるためのものです。
採用側が重視するポイント:
- メンタル・体調管理の視点があるか
- 周囲と支え合えるか
- 成長意欲があるか
- 現実的な視点で“長く働く姿勢”を持っているか
NG回答:
- 「特にありません」「環境が良ければ続けられます」
- 受け身・他責な内容
最も評価されるのは、「自分でできる努力+職場と協力する姿勢」の両方を語れる回答です。
30.当院についてどのような点を調べてきましたか?
「ホームページを拝見し、御院が“地域医療の質向上”や“患者中心の看護”を大切にされている点に共感しました。また、外来・病棟・在宅の連携や、専門外来の取り組みも参考にさせていただきました。自分の経験が活かせる環境だと感じています。」
「看護部の教育体制や離職率など、公開されている情報を確認しました。スタッフの声から“チームワークを大切にする職場”であると感じ、働くイメージが明確になりました。学びの機会が多い点にも魅力を感じています。」
「施設見学でスタッフの方同士の声かけや患者への対応を見て、落ち着いた雰囲気の中で業務が行われていると感じました。説明も丁寧で、スタッフ間の連携がとれている印象を受けました。自分もここで働きたいと強く思いました。」
解説・ポイント
この質問は “志望度の高さ” を最も正確に測れる質問です。
見られているポイント:
- 事前に応募先をどれだけ調べているか
- 情報を“自分の経験や価値観”と結びつけて語れるか
- 働く姿勢が前向きか
NG回答:
- 「特に調べていません」
- 「家から近いので」だけで終わる
- 企業批判や噂話に触れる
ベストは、「理念・診療体制・教育方針・実際の雰囲気」を具体的に挙げ、そこに自分の経験がどのように活かせるかまで言及することです。
面接対策に悩んだら「プロ」に相談しよう
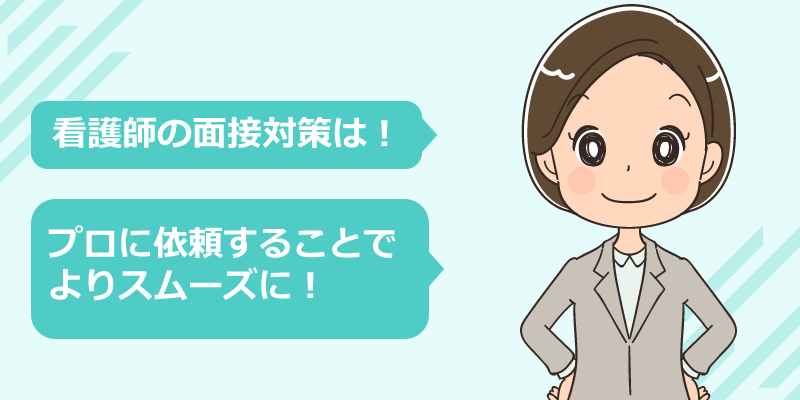
看護師の転職活動では、志望動機・退職理由・これまでの経験の伝え方など、面接の準備で不安を抱く方が非常に多いです。履歴書や職務経歴書の書き方も含め、一人で対策を進めるよりも、看護分野に特化した「プロ」に相談する方が圧倒的に成功率が高くなります。
多くの看護師は、転職サイトを「求人紹介をしてもらう場所」と捉えがちですが、看護師転職サイトでは面接対策や応募書類の添削まで総合的にサポートしてくれます。
面接対策は、単に「回答例を覚える」だけでは不十分です。医療機関の面接では、入職後の協調性や患者対応の質、職場文化との相性を重視されるため、第三者による客観的な視点でのアドバイスが欠かせません。
また、以下のようなサポートは独学では得られないため、特に初めての転職では大きな力になります。
- 面接時の服装や立ち居振る舞いのアドバイス
- 質問に対する「その方らしい回答」の整理
- 病院側の評価ポイントを踏まえた模擬面接
- 履歴書・職務経歴書の添削(志望動機の整合性チェック含む)
- 面接同行・面接後のフィードバック
医療現場は専門性が高く、看護師自身も看護分野の知識には長けています。しかしその一方で、ビジネスマナーや言語化のスキルに自信がないまま面接に挑み、不利になってしまうケースが少なくありません。
新卒であれば多少の不慣れは許容されますが、中途採用では「年齢相応の常識・礼節」が求められます。面接官にその部分で不安を与えてしまうと、選考結果に大きく影響します。
だからこそ、転職を成功させたい場合は、看護師転職の支援実績が豊富なプロに相談し、第三者の目線で面接準備を整えることが最も安全で確実です。
履歴書・面接対策が充実!レバウェル看護
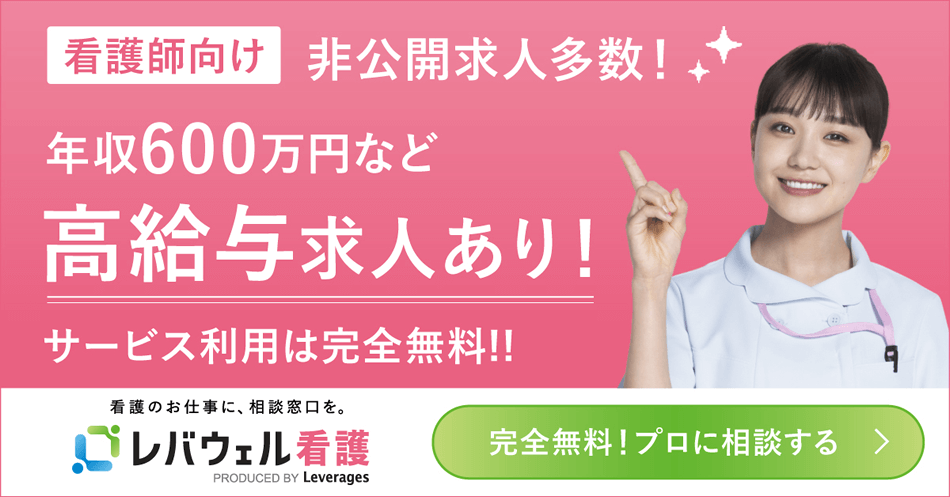
| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
|---|---|---|---|
| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |
|---|---|
| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |
| 公開求人数 | 128,809件(2026年2月2日時点) |
| 非公開求人 | 豊富 |
| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |
| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤 |
| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |
| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |
| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |
| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |
「レバウェル看護」は全国規模で看護師の利用者数が多く、応募書類の添削や面接対策の質が非常に高いのが特徴です。年間5,000件を超える医療機関へのヒアリングを行っているため、病院ごとの特色に合わせたアドバイスを受けやすく、面接で聞かれやすいポイントも事前に把握しやすい強みがあります。
模擬面接・面接同行も柔軟に対応しているため、初めての転職で不安が大きい方でも安心して準備が進められます。
公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/
看護師のリアルな転職支援に強い!ナース専科 転職

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
|---|---|---|---|
| サイト名 | ナース専科 転職(旧 ナース人材バンク) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |
| 公開求人数 | 20万件以上 |
| 非公開求人 | 豊富(会員限定のレア求人あり) |
| 対応職種 | 正看護師、認定看護師、准看護師、助産師、保健師、管理職 |
| 対応 勤務形態 | 常勤、常勤(日勤のみ)、常勤(夜勤あり)、常勤(夜勤のみ)、非常勤 |
| 対応施設 | 病院、クリニック、訪問看護、企業、保育園、幼稚園、学校、その他 【介護施設】 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、訪問介護事業所、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、デイケア事業所、小規模多機能、訪問入浴事業所、看護小規模多機能居宅介護、有料老人ホーム、デイサービス事業所、グループホーム、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者専用住宅、ショートステイ事業所、訪問リハビリ事業所、介護医療院 |
| 対応 診療科目 | 美容、産婦人科、整形外科、眼科、外科、呼吸器科、循環器科、精神科/心療内科、小児科、皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、消化器科、内科、透析、その他 |
| 対応配属先 | 病棟、外来、オペ室、透析、その他 |
| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 特徴 | ・東証プライム上場企業 ・支店が多く地域密着&チーム制で転職をサポート ・職場のリアルな情報を共有することも可能 ・2025年オリコン顧客満足度®調査 看護師転職3年連続No.1 ・LINE対応 |
「ナース専科 転職」は、大手看護師向けメディア「ナース専科」を運営する会社が提供している転職サービスで、看護師向けの情報量が圧倒的に多いのが強みです。病院・施設の口コミや実際の転職事例に基づいたアドバイスを受けられるため、面接でよく聞かれる質問や、応募先との相性判断にも役立ちます。
応募書類の添削や模擬面接、面接同行などのサポートも充実しており、「どのように話せば自分の強みが伝わるか」を一緒に整理してくれます。初めての転職の方はもちろん、ブランクがある方やキャリアに迷いがある方にも利用しやすいサービスです。
公式サイト:https://www.nursejinzaibank.com/
まとめ
看護師の転職面接では、面接官に「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるかどうかが大きなポイントになります。そのためには、よくある質問に対して事前に考えを整理し、自分の経験や看護観を自分の言葉で伝えられる準備が欠かせません。
面接では、答えそのものよりも「表情・姿勢・言い回し」など、話し方の印象が評価に影響することもあります。質問意図を理解し、ネガティブな伝え方を避けながら、前向きで誠実な姿勢を示すことが重要です。
また、緊張して聞き返しても問題ありません。「質問の意図が正しく理解できているか」を確認しながら、落ち着いて会話を進める方が、むしろ好印象につながる場合もあります。
事前に回答を準備し、声に出して練習することで、面接当日も自然に話しやすくなります。どの質問でも「相手が何を知りたいのか」を意識しながら、落ち着いて、はっきりと回答できるよう備えておきましょう。
関連リンク
このサイトの運営者情報
| 運営会社 | 株式会社peko |
|---|---|
| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |
| 代表取締役 | 辻󠄀 昌彦 |
| 設立 | 2015年6月 |
| 資本金 | 14,000,000円 |
| 事業内容 |
|
| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |
| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |
| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |
| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |